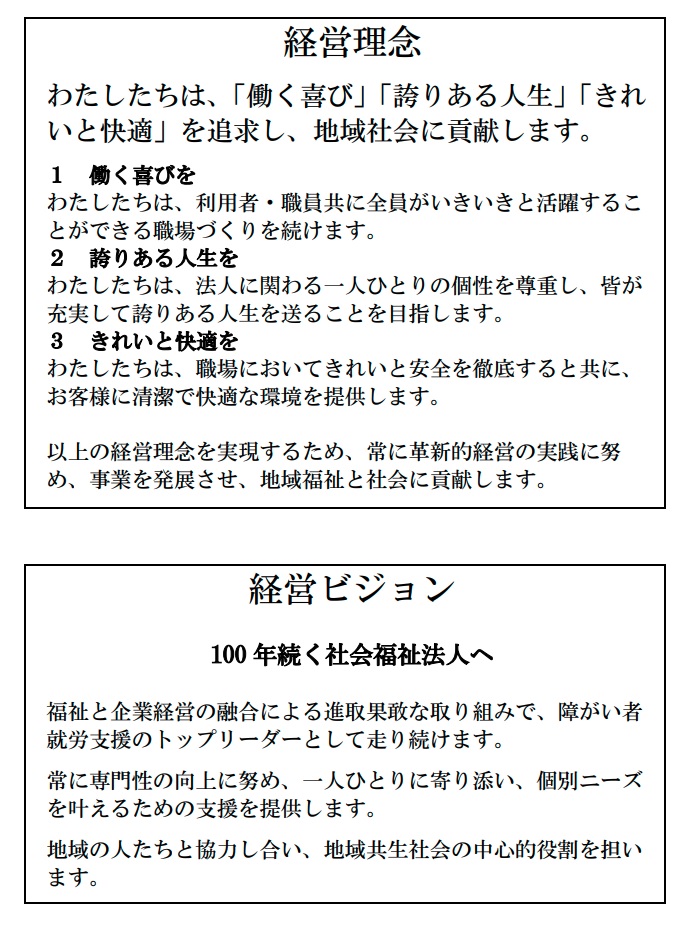創業者の髙江常男は、小学校のときに竹とんぼがあたったことで右目を失明。送電工事に携わっていた17歳のときには3,000ボルトの高圧電線で感電し、両腕を失いました。
しかし口にペンを咥えて取材に歩くなか、炭鉱事故でケガをして仕事を見つけることができずにいる身体障がい者の存在を知り、彼らの仕事探しに奔走するも雇ってくれる会社はなく、「それなら自分たちで働く場をつくろう」と苦労して立ち上げたのが「赤平ドライクリーニング工場」でした。
創業当初は資金繰りにも苦しみ、何度も苦境に立たされましたが、その都度熱い情熱で乗り切り、北海道光生舎は次第に発展していきました。高度成長期の波にも乗り、積極的な営業戦略と近代的な設備投資で、北海道内でトップクラスのクリーニング事業を営むまでになったのです。
平成12年1月突然の脳梗塞で倒れ、そのまま意識が戻ることはなく、倒れてから6年6か月後の平成19年7月、愛する家族に見守られながら静かに息を引き取りました。享年80歳の生涯でした。
目標を成し遂げる強靭な意志と不屈の精神
創業者の髙江常男氏は、10歳の頃に右目に竹とんぼを刺して片目は義眼であり、事業を興したときは両手のない障害者であった。
昭和19年の17歳のとき、電気事故の為両手を失った。中標津付近に空港の建設をするための電気工事の仕事に従事し、高い鉄塔に登り電線を張るという工事をしていた。
その時に、本来であれば電気が流れていないはずの電線に3000ボルトの電気が流れており、それを両手で掴んだ瞬間、本人は意識がない状態 となる。通常であれば3000ボルトの電気に感電した段階で即死であろう。運よく一命は取り留めたものの、両腕を切断することになった。
両手がなくなった人間が、戦後どうやって生きて行ったら良いのか。普通の仕事はできないので、詩や小説等を書いて生きていくことを考 え、口にペンをくわえて字を書く練習を始めた。本人は、尋常小学校しか出ていないため、百科事典などの本で勉強をして、なんとか作家として生きていこうと 考えた。
医者や占い師から、こんな大病をした者はせいぜい生きても10年だと言われたので、睡眠時間を削るしかないと考え、眠くなると足に針を刺したり、 冷水に顔をつけたりして1日4時間という睡眠時間で、口で字を書く練習をし、本を読み、詩を書いたのである。
当時は、炭鉱が全盛の頃で、地元の赤平で炭鉱の仲間と共に詩集などを出していた。たまたま、その中に地方紙の新聞の編集長がいて、新聞記者と して職を得ることができた。障害により仕事が出来なかったものが職を得る喜びと、人として仕事をすることの重要さを味わった瞬間であった。
その後編集長になり、赤平の町を記事を書きながら歩くことになる。当時は炭鉱全盛だったが、エネルギー革命で徐々に斜陽化していた時代である。町には、炭鉱事故で怪我をした障害者がたくさんいた。彼らに、なんとか就職を斡旋しようと思うが、どこも雇ってくれる所はなかった。
「両手のない自分が仕事を見つけてようやくメシ が食えるようになった。今度はこの障害者の人たちの仕事をなんとかして見つけたい。それが叶わないなら自分たちで仕事をやるしかない」と、創業を決意する。
クリーニングの仕事を選んだ理由は、1つに、家族経営のクリーニング屋が多かったため、機械化によって大量生産をすれば、障害者でも一般の人に負けない生産性を上げることができると考えたためである。
2つ目は、クリーニングはたくさんの工程に分けられるので、片手のない人は片手のいらない仕事、足の悪い人はそれにあった仕事というように、作業の細分化ができると考えた。
最後に、当時は高度経済成長時代だったので、これから日本人は豊かになり、必ずたくさんの服を着るであろう。将来的にクリーニングの仕事は絶対伸びると考えたのである。
命までもかける強烈な使命感
十数名の障害者が集まったが、まったくお金がない。このため、銀行などへ資金調達に奔走するが、どこも相手にしてくれない。ようやく当時の労働金庫の赤平支店長が話しを聞いてくれた。
集まった障害者たちも以前は炭鉱の組合員だったということで、札幌本店で融資審査受けることになる。本店審査を受けるとき、もし本店の審査に落ちお金を借りることができなかったら、札幌の高架線から身を投げて死のうと決意し出かけたのである。
「俺はお金が借りられなかったら死ぬ気だった。だから命がけで話をした。しかし銀行の人間は所詮サラリーマンだ。この人間に金を貸しても大丈夫かどうかという目で俺を見ていた。
生きるか死ぬかの話をしている人間とは迫力が違う。俺の話を目を白黒させながら聞いていた。そして融資をしてくれることになった」というのである。
その足で、伴侶となる美穂子に会いに行った。美穂子が結婚を決めたのは、この時の常男の目がすごく輝いていたからだという。結婚して両手のない常男の面倒を一生みようと思ったということである。
明確な差別化と迅速な環境適応
営業方法は通常の営業では勝てないため、店を出すのではなく一軒一軒訪問してクリーニングの注文をもらうという外交方式をとる。始めると仕事はどんどん入って来たが、運転資金不足に悩まされる。
「金には血反吐を吐く思いをした」のである。創業から2年ぐらい経ったときに、身体障害者の授産施設の認可をとると補助金が出る制度の事を知らされる。道庁の人間と協力してなんとか現在の北海道光生舎という施設の認可をもらった。この補助金によっ て、ようやく一息つくことが出来た。
10年ほど経って、ある程度会社の規模が大きくなったときに、業界の反対運動が起きる。競合のクリーニング会社から反授産運動が起き、営業の会社を株式会社、工場の方は授産施設に分離することになる。
常男は授産施設と営業を分離するということは、授産施設から営業権を奪うことになる。光生舎は良いが将来他の授産施設の発展に禍根を残すことになると反対したが、結局道の課長に説得されてその案を呑むこととなった。
それから営業の会社が別になったので、正々堂々と札幌や他の地域に進出することができ、結果として現在は、北海道で1、2位を争う規模の会社に成長することができた。
果てしないロマンと企業家精神の発揚
創業者は、途中で大きな夢を見る。それは、現在の北広島市にある西の里という団地がある場所に、障害者を1万人くらい集めた「まち」を造ろうという計画であった。
周辺の土地10万坪を買い上げ、整地をして、印刷とクリーニングの施設を立ち上げた。あまりにも壮大な計画であり、資金に行き詰まり断念するが、今でもその「まち」の図面は残っている。
会社や施設を創ろうとか、それを伸ばそうという人はたくさんいるが、「まち」を創ろうと思った人は少ない。そこに、果てしないロマンを感じる。
通常の会社であっても、10年経てば7割以上が倒産をしてしまう。20年経って残っている会社は、ほんの数パーセントである。障害者だけが集まって会社を創ってここまで伸びるということは、ほとんど奇跡に等しいだろう。
障害者になんとか仕事をさせたいという命がけの強烈な使命感、はっきりとした目標とビジョン、そして、一番重要なのは、それを成し遂げようとする強烈な意志があったからであり、それは企業家精神と呼べるものであろう。
仕事をすることに対する強い思い入れ
仕事をすることに対する思い入れは、ものすごく強かった。自分の子どもよりも年下の社員に対しても真剣に怒る。それは、仕事に対する強烈な意思、つまり使命感である。
施設は、障害者を雇用しているので、間違いなく終身雇用である。死ぬまで面倒をみることになる。普通の会社だったら潰れても、まだ社員は他に就職ができる。ここでは障害者を抱えて、何百人も仕事をさせている。それが潰れたら、彼らの仕事はどうなるのか。絶対に会社を潰すわけにはいかないという強い意志である。
それは、「自分はどうなってもいい」という思いと一体である。その基盤には、両手をなくすということで、生きるか死ぬか、もしかしたらそれ以上の経験をしていることがある。
新しい施設が建っても古い家屋に住み続け、会社を起こしてからもそこから給料を受けとらず、仕事が終わった後に自分で新聞を書き、株式会社ができるまで、その原稿料で生活していた。
そのような行為の実践が、本当に自分というものを捨ててやっていると実感させるのである。
お客様に対して決して嘘をつかない
「誠心誠意」という社是は、お客様に対して、決して嘘はつかないということである。クリーニングをしているのは障害者の施設であるが、 それを売り物にしてお客様に営業に行ったことは1回も無い。
それは諸刃の剣である。品質が良いものを収めているときは、障害者でもこんな良い仕事ができるのかと言われるが、一度悪いものを収めたときに、やっぱり障害者だからこんな仕事しかできないと言われる。
お客様には障害を売り物にせず、他の会社とは品質と価格で正々堂々と戦って勝たなければ生き残れない。
日々悔いを残さずに生きる
「努力敢闘」という社是は、今日1日努力敢闘したと言い切れるかということである。創業者は、今死んで悔いが残るような生き方をしたことはないと言った。
今やれることを日々精一杯やっているので、今もし死んでも、悔いが残るような生き方をしていないのである。
常に新しいものを創造する
「創造実践」という社是は、企業は常に新しいものを創造しなければならないということである。それには、まず実行してみることである。
創業者は、会社の中で一番年上であったが、一番新しいことに取り組むことが好きだった。新しいものを取り入れていこうという感覚は、会社の中でも一番強かったのである。